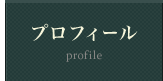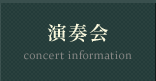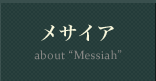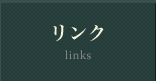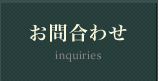プロフィール(合唱団・指導陣)
■マヨラ・カナームス東京 / majora canamus tokyo

ラテン語「majora canamus = 大いなる調べを歌おう」の名を冠し、2012年9月、東京を本拠地に設立された合唱団および音楽団体。音楽監督には、
2014年1月東京・渋谷にて、
2018年2月には、室内楽の殿堂・紀尾井ホールに於いて、モーツァルト未完の遺作≪レクイエム≫を初めて取り上げた。また2021年10月の≪メサイア≫公演は、文化庁/ARTS for the future!対象事業に採用され、コロナ禍を乗り越え久々に生の音楽、合唱に触れた多くの音楽ファンから喝采を浴びた。
団体名の由来ともなるヘンデル≪メサイア≫は、様々なヴァージョンで定期的に演奏し、
■音楽監督: 渡辺 祐介 / WATANABE, Yusuke

東京藝術大学音楽学部卒業、同大学院修了。多田羅迪夫氏に師事。オランダのデン・ハーグ王立音楽院にて、ペーター・コーイ、マイケル・チャンス、ジル・フェルドマン、リタ・ダムスの諸氏のもとで研鑽を積む。
2002年よりバッハ・コレギウム・ジャパンのメンバーとなり、多数の演奏会、録音、海外公演等に参加。2020年3月のヨーロッパツアーではJ.S.バッハ《ヨハネ受難曲》のピラト役を務め、特にロンドン公演においては「エネルギーを緩慢なく漸増させ、物語を最高潮へと持ち上げていく役割を果たしきったのだ」と英ガーディアン紙に評される。
いっぽう若い世代のピリオド楽器のスペシャリストが結集したオーケストラ「オルケストル・アヴァン=ギャルド」では2019年のオーケストラ創設以来音楽監督を務め、ベートーヴェンの作品演奏に集中的に取り組んでいる。特に2020年11月に横浜みなとみらいホールでのベートーヴェン《交響曲第9番》(令和2年度文化庁芸術祭参加)、2021年8月に東京藝術大学奏楽堂で行われた劇付随音楽《エグモント》(ゲーテの原作戯曲との全曲上演)、2022年3月に同じく藝大奏楽堂にて、宝生流能楽師で同大学教授の武田孝史氏の能舞とのコラボレーションによる《ミサ・ソレムニス》上演を行うなど、ベートーヴェンの大作を次々に手がけ、いずれも絶賛を博した。
現在マヨラ・カナームス東京音楽監督、東京ムジーククライス常任指揮者、東京クローバークラブ指揮者、オルケストル・アヴァン=ギャルド音楽監督。声楽家としては古楽アンサンブルCantus Ebrius、Seven Tears Consort主宰、Coro Libero Classico、Bona Musicae Membra各メンバー。
■オルガニスト: 新妻 由加 / NIITSUMA, Yuka
東京藝術大学オルガン専攻卒業。同大学院器楽専攻修士課程修了後にスイスのバーゼル市立音楽院スコラ・カントルムにてオルガンの歴史的奏法を学び、その傍らバーゼル市近郊のカトリック教区でオルガニストを務めた。2015年と2017年にバーゼル市教会音楽協会H. バルマー財団奨励賞(オルガン部門)受賞。2017年オーストリア国際H. I. F. ビーバーコンクール(アンサンブル部門)最優秀賞。
現在は東京を中心とした演奏・指導のほかオルガン通奏低音奏者としての活動も数多く、2024年に「Salicus Kammerchor」、「プロムジカ使節団」の両団体が各々スタートさせたJ. S. バッハのカンタータ全曲録音プロジェクトにも継続的に参加している。日本聖公会聖マーガレット教会、立教新座中学校・高等学校オルガニスト。
■ヴォイストレーナー: 中江 早希 / NAKAE, Saki
(©︎AyaneShindo)
北海道出身。北海道教育大学岩見沢校芸術課程音楽コース声楽専攻卒業。東京藝術大学大学院修士課程音楽研究科声楽専攻独唱科、同大学院博士後期課程を修了。在学時ハンス・アイスラーの歌曲を研究し大学院アカンサス賞、三菱地所賞受賞。第14回日本モーツァルト音楽コンクール声楽部門第2位。第78回日本音楽コンクールオペラ部門にて入選。第12回中田喜直記念コンクールにて大賞を受賞。第25回ハイメス音楽コンクールにて声楽部門第1位。第3回ジュリアード音楽院コンクール第1位。旭川市新人音楽賞、第27回道銀芸術文化奨励賞受賞。国内外数々のオーケストラや指揮者と共演。レパートリーは宗教音楽からオペラ、現代音楽などのソリストを務めるだけではなく、ドラマやゲーム音楽など多くの作品にヴォーカルとして携わる。モーツァルトのコンサートアリアを歌った鈴木秀美指揮オーケストラリベラ・クラシカの自身初のライブ録音のCDが特選盤に選出されている。バッハ・コレギウム・ジャパン声楽メンバー。また、北海道上川郡鷹栖町ふるさと応援大使としても活動をしていて、演奏活動を通じて音楽や地元である鷹栖町の魅力を発信し続けている。洗足学園音楽大学非常勤講師。
■ヴォイストレーナー: 高橋 ちはる / TAKAHASHI,Chiharu
東京藝術大学大学院博士後期課程修了。ウィーン国立音楽大学リート・オラトリオ科研究科修了。第15回友愛ドイツ歌曲コンクール入選。第79回日本音楽コンクール入選。第10回中田喜直記念歌曲コンクール大賞並びに中田喜直賞(第1位)受賞。台東区ベートーヴェン《第九》公演にて藝大オケと共演しソリストデビュー後、J.S.バッハ《ヨハネ受難曲》、《マタイ受難曲》、《クリスマス・オラトリオ》、《ミサ曲ロ短調》、ヘンデル《メサイア》モーツァルト《レクイエム》、ヴェルディ《レクイエム》、マーラー《交響曲第2番〈復活〉》《大地の歌》等にソリストとして出演。オペラではフンパーディンク《ヘンゼルとグレーテル》(ヘンゼル役)等に出演。文化庁助成・日本演奏連盟主催によるリートリサイタルを開催し『音楽の友』『音楽現代』の各誌にて「安定した発声と練られた歌唱」「馥郁とした伸びのある声質」と高い評価を得た。バッハ・コレギウム・ジャパン声楽メンバーとして国内外での演奏・録音に参加している。みずほ合唱団、志木第九の会、東京バロックスコラーズ、横浜シティ合唱団の各団にてヴォイストレーナーを務めている。
■ヴォイストレーナー:中嶋 克彦 / NAKASHIMA,Katsuhiko
長崎県大村市出身。福岡教育大学音楽科卒業。東京藝術大学大学院修士課程オペラ科修了。同大学院博士課程オペラ科修了、博士号取得。2012 年より文化庁在外派遣研修員としてドイツに留学、マインツ音楽大学のバロック声楽コースにて研鑽を積んだ。ルネッサンスから現代まで幅広いレパートリーを持ち、なかでも J・S・バッハやヘンデルなど、バロックの作品において多く活躍している。バッハ・コレギウム・ジャパン、ラ・フォンテヴェルデ、コレギウム・ムジカーレ、パーセル・プロジェクト等のメンバーとして国内外におけるコンサートや録音に多数出演している。またオラトリオのソリストとしても定評があり、ヘンデル《メサイア》やベートーヴェン《第九》、ハイドン《天地創造》、メンデルスゾーン《エリヤ》等、国内の主要オーケストラとの共演も多い。オペラにおいては、第 50 回東京藝大大学院オペラ定期公演モーツァルト《コシ・ファン・トゥッテ》のフェルランド役でデビュー。以降、新国立劇場や東京室内歌劇場、サントリーホールオペラアカデミー公演など、オペラの舞台においても活躍している。国立音楽大学非常勤講師。
■ヴォイストレーナー:氷見 健一郎 / HIMI,Kenichiro
(©︎井村重人)
東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院音楽研究科修士課程オペラ専攻修了。新国立劇場オペラ研修所修了。研修中にANAスカラシップ奨学生として、イタリア、ミラノスカラ座アカデミー、ドイツ、バイエルン州立歌劇場付属オペラ研修所にて海外研修を受ける。新国立劇場公演《魔笛》にて、ザラストロ役で本キャストデビュー。バスソリストとして、バッハ《マタイ受難曲》、モーツァルト《レクイエム》、ハイドン《天地創造》、ベートーヴェン《ミサ・ソレムニス》、《交響曲第9番》、ヴェルディ《レクイエム》に出演。オペラではモーツァルトの《フィガロの結婚》バルトロ、《ドン・ジョヴァンニ》レポレッロ、騎士長、《コジ・ファン・トゥッテ》ドン・アルフォンソ、ロッシーニの《セヴィリアの理髪師》バジリオ、ドニゼッティの《ドン・パスクワーレ》タイトルロール、プッチーニの《ラ・ボエーム》コッリーネ、《ジャンニ・スキッキ》シモーネ、團伊玖磨の《夕鶴》惣どなどを演じる。公演では、井上道義、鈴木秀美、高関健、横山奏の各氏と共演。第17回松方ホール音楽賞奨励賞受賞。バッハ・コレギウム・ジャパン声楽メンバー。とやまふるさと大使。
■言語アドヴァイザー:三ヶ尻 正 / TADASHI,Mikajiri
東京大学英文科卒。ヘンデル研究・オラトリオ研究、声楽家の言語指導(英独羅)、対訳・字幕制作に従事。オペラ・オラトリオの政治史的解釈に関する執筆・講演で好評を博す。言語指導は桐朋学園大学、武蔵野音楽大学、京都市立芸術大学大学院、びわ湖ホール、北海道二期会等で行い、音声学に基づく科学的な指導に、字幕・対訳では原典のことばを大切にしたわかりやすい日本語訳に定評がある。著書・訳書に『ミサ曲・ラテン語・教会音楽ハンドブック』、『メサイア・ハンドブック』、『歌うドイツ語ハンドブック』、『ヘンデルが駆け抜けた時代~政治・外交・音楽ビジネス』、『ヘンデル 創造のダイナミズム』(共訳)など。新国立劇場オペラ研修所講師、国立音楽大学大学院および大阪音楽大学大学院非常勤講師。日本音楽学会、日本ヘンデル協会、日本イタリア古楽協会会員。